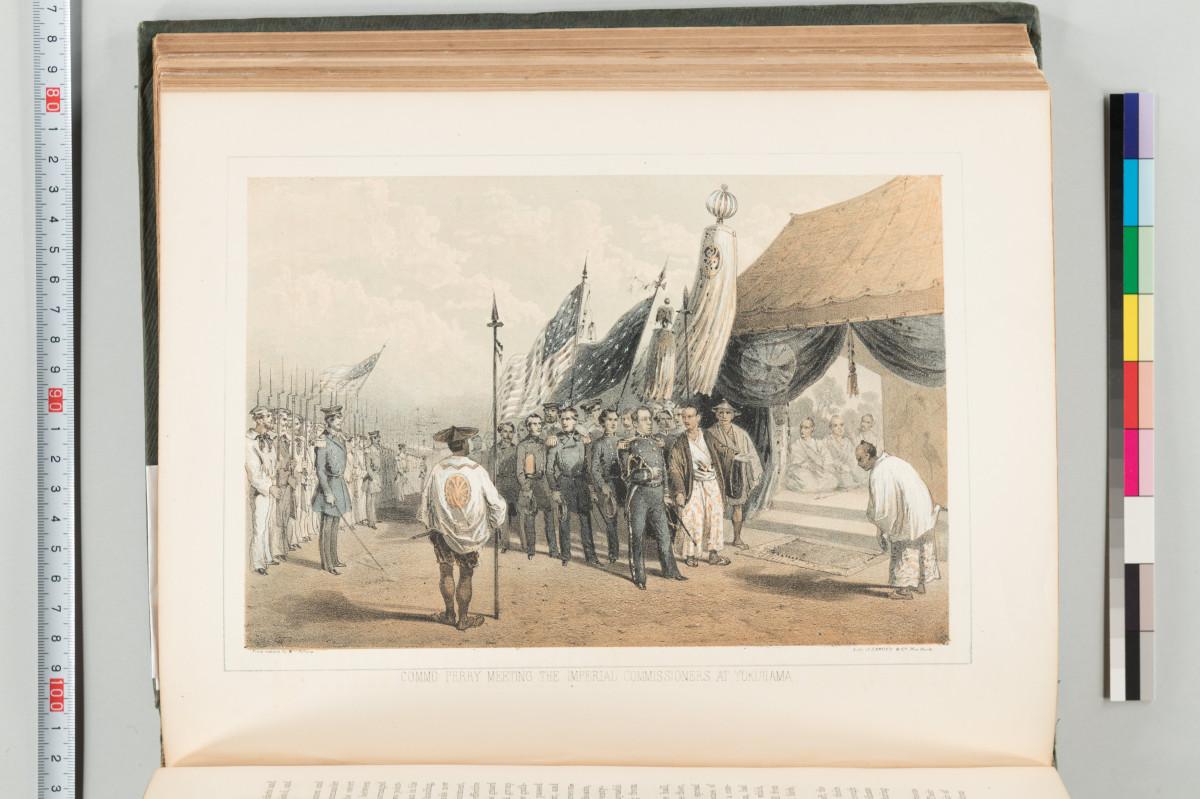【PASS the TORCH 文京アワード2025】第1回 候補者インタビュー 大岩良至さん|子どもたちのふるさとを育む仕掛け人が描く未来
文京区の地域ニュースメディア「文京経済新聞」は「PASS the TORCH」のブランドビジョンを掲げ、見つけた資源を次世代につなげて新しい時代を創ることを目指しています。その一環として、地域の未来を見つめながら、文京のまちに根ざした活動を続けている人を「文京アワード2025」候補者としてインタビュー。次世代に受け継ぎたいまちの取り組みや、その中心にいる人々の思いを紹介していきます。
初回は、地蔵通り商店街でのマルシェや子ども食堂をはじめ、文京区関口のまちづくりに力を注いできた「大江紙業株式会社」社長の大岩良至さん。大人も子どもも笑顔になる「仕組み」をどう育んできたのか。その背景にある原動力と、次世代への思いや未来への展望を伺いました。

「大江紙業株式会社」代表の大岩良至
―大岩さんが現在取り組んでいる地域活動について教えてください。
本業は点字用紙や洋紙など紙の卸売業を営みながら、現在は地域貢献の活動にも取り組んでいます。具体的には、地蔵通り商店街のマルシェへの参加や「子ども食堂」、「こども花まつり」など、子どもを中心に家族や地域の人が集まる場づくりを続けています。
「子どもたちに、ここがふるさとだと思ってほしい」という思いが活動の根底にあります。そのため、地域のつながりを作ること、子どもたちの思い出になる行事を育てていくことに力を入れています。

「大江紙業」で行われたフリーマーケット
―大岩さんが地域活動をスタートしたきっかけは?
きっかけはマンションのエレベーターの中でした。住んでいる住民同士があいさつもせず、顔も名前も知らない。それが「何だかおかしいな」と思ったんです。
まずは、住民同士が顔を合わせる機会を作りたくて、マンション内で小さなバーベキューを企画しました。それが思いのほか好評で、町内会の方々にも活動が知られるようになり、地域のイベントにも関わるようになっていきました。

「正八幡神社例祭」の様子
―マルシェを始めたきっかけや現在に至る経緯を教えてください。
もともと祭りが好きで、町内会や友人の祭りをよく手伝っていました。そんな時に淡路町のマルシェを見学し、「こういう街にしたい」と強く思いました。
特に感心したのは、地域の学生たちが主体的にマルシェを支えていたこと。それを可能にしていた「ボランティアシール制度」という仕組みも印象的でした。お年寄りから学生までが無理なく集まっていて、お茶を飲みながら自然と交流が生まれていた雰囲気も良かった。単なる物販イベントではなく、街に新しい空気が生まれていると感じました。その経験をヒントに、商店街の仲間たちと「関口1丁目活性化協議会」を立ち上げ、マルシェを始めました。
最初は補助金を頼りに、「お願いします」「ごめんなさい」「よろしくお願いします」「ありがとう」の精神で進めました(笑)。焼き芋の屋台がSNSで話題になり、子どもたちも仕込みから販売までを手伝ってくれて、今も地域の交流の場として続いています。

「江戸川橋地蔵通りマルシェ」の様子
―マルシェを立ち上げた後、こども食堂も始めていますね。そのきっかけや運営スタイルについて教えてください。
ある時、1,000円札を握りしめて毎日コンビニに通う子どもの姿を見かけ、両親が共働きで忙しく、子どもが一人で食事をしていることが分かりました。
それで「これは何とかしたいな」と思ったんです。居酒屋「源」さんに昼間だけ場所を貸してもらい、地域の方々から食材を持ち寄って始めたのが「こども食堂」の始まりです。今では3つの町内会と「社会福祉法人三幸福祉会 杜の癒し文京関口」、明治大学ボランティアサークルの学生たちに協力してもらい、手作りの食事を通じて子どもたちを見守る活動になっています。

居酒屋を借りて始まった地域の食事会
―桜の季節に江戸川公園で開催される「江戸川公園花まつり」に合わせて「こども花まつり」も始まりました。
『江戸川公園花まつり』に地域の親子で楽しめる催しを加えようと、2年前に『こども花まつり』がスタートしました。近隣の町内会同士をつなぎ、親子が一緒に楽しめるイベントです。
江戸川公園の利用に当たっては、音出しやキッチンカーの使用など制約も多くて区とのやり取りもありましたが、安全面に配慮して地元の手作り感を大切に運営しています。子どもたちの笑顔が何よりの励みになっています。

「江戸川公園花まつり」の様子
―大岩さんは、なぜこれだけ精力的に地域活動に力を入れているのでしょうか?大岩さんの思いとは?
「ふるさと」と呼べる街を子どもたちに残したいからです。子どもたちが成長して、大人になった時に「僕の、私のふるさとは文京区・関口です」と胸を張って言ってくれたら嬉しい。そのためには、普段から「こんにちは」とあいさつできる関係が必要です。

「正八幡神社例祭」の様子
―地域で活動してこられて、改めて文京区にどんな魅力を感じますか?
山手線の内側に位置し、どこへ行くにもアクセスが良いことが一つ。
そして、もともとの住人より、新しく引っ越してくる方の方が多い地域だからこそ、オープンで柔らかい雰囲気がある。新しい住民の方々も「自分のふるさとだ」と思える街に育てていく余地があるところも、文京区の魅力だと思います。

神田川の関口大洗堰があった跡付近
―今後の課題はありますか? 課題をクリアしながら、より良いまちになるためにはどうすれば良いとお考えですか?
活動の中心が特定の人に集中しすぎている現状が課題です。自分が倒れたらどうなるのか…。そんな危機感もあります。
地域活動も企業の事業承継のように、親世代やPTAのつながりを生かしながら少しずつ関わる人の輪を広げ、自然な形でバトンを渡していける仕組みづくりが必要だと感じています。

関口水道町の由来の看板
―最後に、大岩さんにとっての「PASS the TORCH 」、次世代へのメッセージをお願いします。
私は以前「文京区全体をテーマパークにしたい」という話をしたこともありました。今もそのくらい、楽しく愛着の持てる街にしたいという気持ちで活動を続けています。だからこそ、仕組みづくりは楽しみながら。活動が楽しくないと、続けることはできません。
これまで私が作り上げてきたものはありますが、これをベースにしながらもこれからの展開は次世代の皆さんが楽しめることをやってほしい。楽しいこと、必要なことは時代によって変わっていきます。
それでも、根っこの部分は同じ。気がつけば、いざ震災などが起きたときには頼りになるおじちゃん・おばちゃんたち、「ご近所さん」がたくさんいる。自然とそんなつながりを作っていってほしいですね。